ビジネスの現場や学校の課題などでよく目にする「打合せ」と「打ち合わせ」という言葉。あなたも「どっちが正しいの?」と迷ったことがあるのではないでしょうか。筆者もお客さんへの提案書を作成するときに「打合せ」と「打ち合わせ」の表記でよく悩んでいました。言葉は小さな違いでも印象を大きく変えることがあります。
実はこの2つ、どちらも誤りではありません。ただし、使い方にはルールがあるのです。
この記事では、「打合せ」と「打ち合わせ」の正しい使い分け方を、国の基準や実際のビジネス文書の例をもとにわかりやすく解説していきます。自信を持って使えるようにしておきましょう。
この記事ではこんなことが分かります。
- 「打合せ」と「打ち合わせ」のどちらが正しいのか
- 「打合せ」と「打ち合わせ」はどのように使い分けるのか
- ビジネスシーンや公用文で正しいのはどちらか
「打合せ」と「打ち合わせ」はどっちが正しい?
結論からお伝えすると、「打合せ」と「打ち合わせ」は名詞か動詞かによって使い分ける必要があります。
名詞(予定や会議など)として使う場合:
・「打合せ」…公用文における正式な表記
・「打ち合わせ」…一般的で広く使われる表記
動詞(行動を表す)として使う場合:
・「打ち合わせる」…基本形として最も正確な表記
・「打合せる」や「打ち合せる」…一応は許容されるがやや古風、または避けた方が無難
このように、文の中で「打合せ」がどんな役割を果たしているかによって、正解が変わってきます。
最も基本となる2つのパターン
まずは、「名詞」と「動詞」でどう表記が変わるのか、基本的なルールをしっかり押さえていきましょう。
1. 名詞の場合:「打合せ」または「打ち合わせ」
名詞としての「打合せ」は、「ミーティング」「会合」といった意味で使われます。
たとえば、「明日の打合せは何時からですか?」というような使い方ですね。
この場合、正式な公用文では「打合せ」と漢字で書くのがルールです。一方、柔らかく伝えたい場面では「打ち合わせ」と表記されることも多く、会話やメールではこちらの方がよく使われています。
2. 動詞の場合:「打ち合わせる」が基本形
動詞として使う場合、「打ち合わせる」がもっとも正しい表記とされています。
たとえば、「次回の進行について打ち合わせる必要があります」といった表現です。
送り仮名をしっかりと残すことで、動詞としての活用がわかりやすくなり、文法的にも正しい形になります。
誤用として注意したい表記もある
使い分けを間違えると、相手に「文章が雑な印象」を与えてしまうかもしれません。たとえば、以下のような表記は避けた方が無難です。
- ❌「打合わせ」 ✅「打合せ」
- ❌「打ち合せ」 ✅「打ち合わせ」
これらは、名詞としても動詞としても曖昧な形で、正式な文書では推奨されていません。特にビジネスシーンでは注意が必要です。
公的に定められた送り仮名のルールとは?
では、どうして「打合せ」と「打ち合わせ」のように、複数の表記が存在するのでしょうか? それは、政府が定めた「送り仮名」のルールによって説明できます。
根拠:文化庁の内閣訓令(2010年)
2010年11月30日に文化庁が発表した内閣訓令によれば、「常用漢字表」に基づいた文書では「打合せ」が正式な表記とされています。
つまり、公的機関が出す通知や資料、行政文書などでは「打合せ」と漢字表記で書くのが正しいとされています。
これは、文体の統一性を保つ目的があり、意味を読み違えることがない場合には送り仮名を省略するというルールに基づいています。
一方で、意味の誤解が生じにくい複合語では、「打合せる」「打ち合せる」も許容されていますが、やや古い印象や非推奨のケースもあるため、無難にいくなら「打ち合わせる」と書いておくのが安心です。
使い分けの実例とポイントまとめ
ここでは、「打合せ」と「打ち合わせる」を実際の文章でどのように使うかを確認していきます。公文書、ビジネス文書、日常会話など、使われる場面ごとに見ていくと、より理解が深まります。
【名詞】打合せ・打ち合わせの使い方
公文書・ビジネス文書での例文
公的な文書や正式な書類、業務フローなどでは、文体を統一するためにも「打合せ」という表記が推奨されます。
例:
・「本日の打合せ議事録を添付いたします」
・「次回の打合せは◯月◯日を予定しております」
一般会話やメールでの例文
一方、メールやチャット、会話の中では「打ち合わせ」の方が自然に感じられることが多いです。堅苦しさを避けたいときに適しています。
例:
・「午後に打ち合わせって入ってますか?」
・「じゃあ、その後にもう1回打ち合わせしましょう」
【動詞】打ち合わせるの使い方
自然な文章例とNG例
動詞で使う場合、「打ち合わせる」が正しい形です。次のように文の中で活用されます。
正しい例:
・「進行内容を打ち合わせる必要があります」
・「明日までに打ち合わせておきましょう」
NG例:
・「内容を打合せる」→ 一応許容されるが、読みづらく不自然な印象があります
なぜ「打ち合わせる」は送り仮名が必要なのか
動詞として活用する場合、「打ち合わせる」は文法上、送り仮名が不可欠です。
「〜ます」「〜た」「〜て」などの活用形に変化させるためには、送り仮名が存在しないと成り立ちません。たとえば、「打合せた」と書いてしまうと、意味はなんとなく通じても文法的には不自然です。
特に就職活動やビジネスメールで誤った活用をしてしまうと、相手に「日本語があやしい人」という印象を与えるリスクもありますので注意しましょう。
ビジネスシーンではどちらを使えばいい?
「打合せ」と「打ち合わせ」、実際の現場でどう使い分ければいいのか――迷うポイントですよね。ここでは、メールや議事録、チャットなど、ビジネスの場面ごとの最適な使い方を解説します。
ビジネスメール・議事録に適した表記
ビジネスメールや報告書では、「打合せ」という表記がよく使われます。これは、見た目が引き締まっており、読みやすく、何より公用文ルールに則っているからです。
ただし、クライアントとのやり取りや、親しみやすさを求める社内チャットでは「打ち合わせ」と書いても問題ありません。
社内と社外での使い分けが必要な理由
文章のトーンは、相手との関係性によって変わります。たとえば、役所への提出資料や官公庁とのやり取りでは「打合せ」が基本。一方、社内メールや上司・同僚とのカジュアルなやり取りでは「打ち合わせ」の方が自然です。
大切なのは、TPO(時・場所・相手)に合わせて適切な表記を選ぶことです。
迷ったら「打合せ」と「打ち合わせる」でOK
「もうどう書いたらいいか分からない…」というときは、以下の基本だけ覚えておけば安心です。
- 名詞 → 打合せ
- 動詞 → 打ち合わせる
この2つのルールさえ守っておけば、公文書・ビジネス文書・日常表現のどれでも恥をかくことはありません。
「打合わせ」や「打ち合せ」は使ってもいい?
似たような表記として、「打合わせ」や「打ち合せ」がありますが、これらは原則として誤用とされます。
許容されない誤記の代表例
文化庁の告示によると、「打合わせ」「打ち合せ」は読み間違いや混乱を招くため、公用文では使用が認められていません。
実際、これらの表記は検索エンジンでも揺れが多く、SEOの観点から見ても統一しておくことが重要です。
間違えると信頼を損なう理由
ちょっとした誤字や送り仮名の違いで、文書全体の信頼性が損なわれてしまうこともあります。
とくに社外に出す資料や、履歴書、報告書などでは細かいところまで注意が行き届いているかが問われるため、正確な表記を心がけましょう。
まとめ:「打合せ」と「打ち合わせる」を正しく使い分けよう
ここまで、「打合せ」「打ち合わせ」「打ち合わせる」などの表記について、名詞と動詞の使い分け、公的ルール、実例まで詳しく見てきました。
見慣れた言葉であっても、文脈によって正しい表記が異なることがわかりましたね。
公的基準に基づく正しい表記をおさらい
ポイントをもう一度整理しておきましょう。
- 名詞として使う場合、公用文では「打合せ」が正式
- 動詞として使う場合は「打ち合わせる」が基本形
- 「打合わせ」「打ち合せ」は誤用とされるので注意
送り仮名を意識するだけで文章力が上がる
文章の中で送り仮名まで意識できるようになると、読みやすく、伝わりやすい文章が書けるようになります。特にビジネスの現場では、メールや資料の表現力がそのまま評価に直結することも少なくありません。
日々のちょっとした言葉遣いに気を配ることで、あなたの文章力と信頼性は格段にアップするでしょう。ぜひ、「打合せ」「打ち合わせる」のような表記の違いも意識しながら、確かな言葉選びを身につけていってくださいね。
面白い漢字の雑学
木へんを使う漢字で興味深い漢字に「櫆」があります。木へんをとって鬼辺になると「魁」になるのですが、読み方や意味をご存じですか?鬼辺の漢字ってどんな意味があるのか気になりますよね。『「櫆」のきへんなしの漢字「魁」(かい)の意味と名前としての使われ方を徹底解説』で詳しく解説しているの一度見てみてください。
筆者は固定概念だけで漢字を判断してはいけないなと痛感しました。
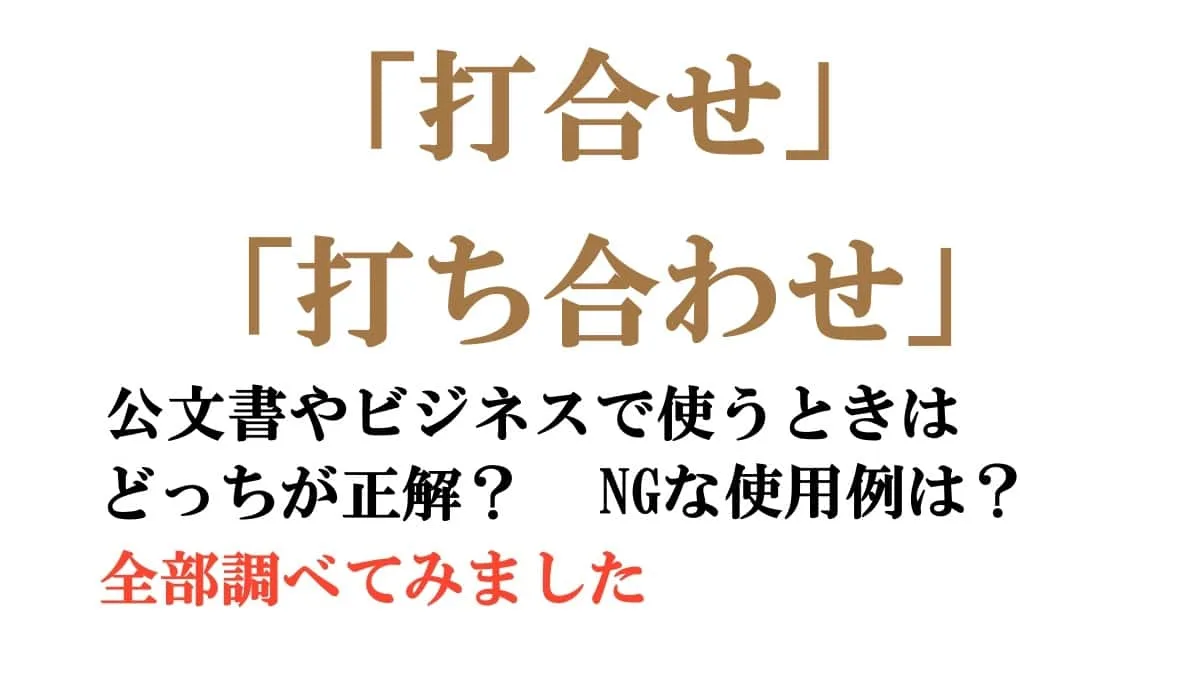

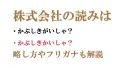
コメント